2024年11月17日に受験した日商簿記1級が合格していました。
今回は私が日商簿記1級を合格するためにした勉強方法や教材についてなどをお伝えいたします。
勉強期間について

期間にして2年かかりました。
勉強をスタートしたのは2023年1月からで、2023年4月から本格的に開始し、2024年11月の受験で合格です。
勉強時間は全く計測していませんがトータルで1000時間は超えていないと思います。
使用した教材について

基本的に全経簿記上級を勉強した際に使用したものと同じものです。
そのため、前回作成した全経簿記上級の記事を参考にしていただければと思います。
以下は、全経上級では使用しなかったもののみを掲載します。
日商簿記1級過去問題集
言うまでもないことですが、過去問題集は必須だと思います。
日商簿記1級の出題のされ方等の癖を見るのに最適です。
また、たまに出題ミスだと感じたり定義が不十分だと感じられる部分が多々あります。
何も知らずに受験するよりは、過去問題集で割り切って問題に取り組むという練習にもなるかもしれません。
網羅型完全予想問題集
日商簿記2級を合格した際にもこちらの2級のものを使用していました。
幅広い出題範囲で過去問題集ではカバーできない範囲もこちらで対応できます。
ちなみに、他の予想問題集等も購入しましたが、後述する理由によりほとんど使用しませんでした。
勉強方法について
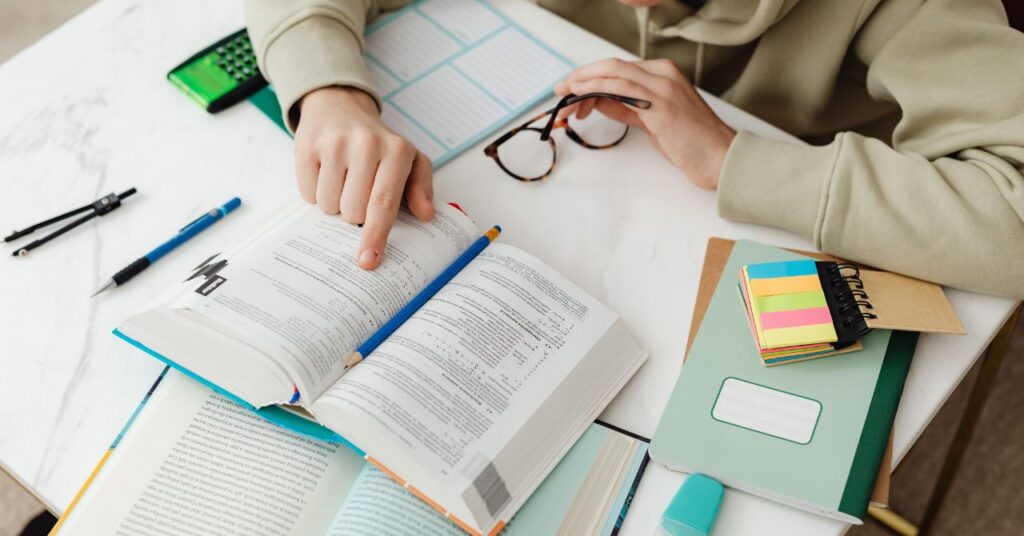
3度にわたり受験したので、その回ごとに何をしていたかご説明します。
1回目の受験のとき
2023年11月が受験日でした。
テキスト・問題集が一通り完結したのが9月末頃で、そこから過去問題集に手を出しました。
ですが、全く歯が立たなかったため、その都度テキスト・問題集を見返し一つ一つ解いていったのですが結局試験日まで時間が足りず不合格となりました。
不合格の原因としては単純に勉強時間不足だったかと思います。
2回目の受験のとき
2024年6月が受験日でした。
2024年2月に受験した全経簿記上級が合格しており、気を抜いていたのかもしれません。
あまり勉強に身が入らず、ゴールデンウィーク頃から本格始動し過去問題集や予想問題集を中心に勉強していました。
結果として、会計学で出題された分配可能額や企業結合、工業簿記の圧倒的な情報量、原価計算の数字が全く合わないなど、いろんな面で点数が取れず不合格でした。
3回目の受験のとき
今回合格した2024年11月の受験です。
改めて記事にしますが、8月に税理士試験の簿記論と財務諸表論を受験しました。
特に簿記論の総合問題の練習は、日商簿記1級の商業簿記の練習にぴったりでした。
6月に比べ、問題を解く速度が圧倒的に変わったのを実感しました。
税理士試験が終わってから本格的に勉強を開始。
今回は試験日まで時間に余裕があったため、以下の勉強法を2週行いました。
- CPAラーニングのテキストに掲載されている例題と問題集を解く。
- 次に、1と同じ範囲の問題を合格トレーニングを解く。
今までの不合格の原因に基礎力が不足していると感じられる部分が多かったためこの方法にしてみました。
10月ごろから過去問題集や網羅型問題集に手を出し始めましたが、上の勉強手順は並行して行っています。
なお、CPAラーニングで出題可能性が低いとされているC論点についても取り組んでいます。
予想問題集のうち網羅型以外を使わなかった理由
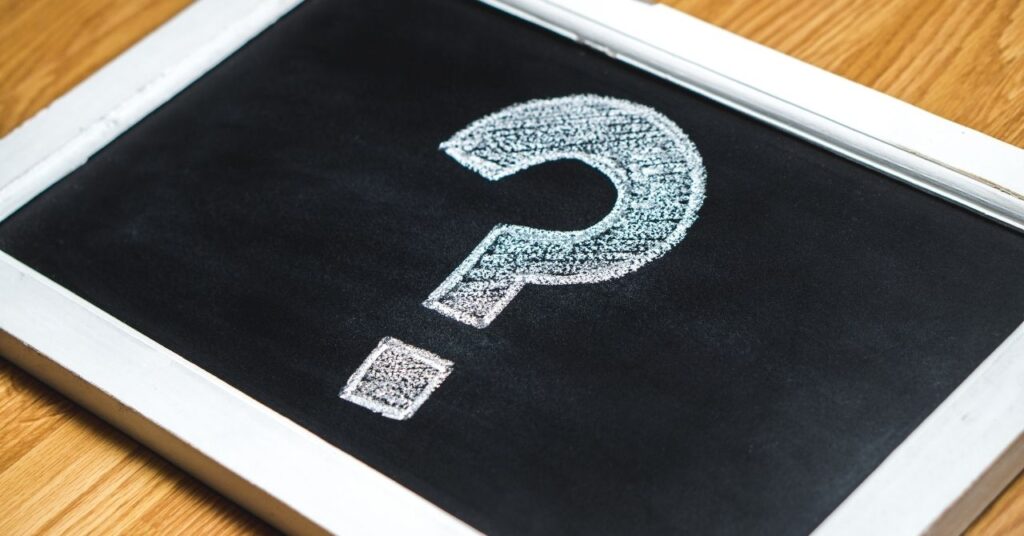
過去問の焼きまわしに感じられるものが多いこと、その予想問題集で解けないものは網羅型等の他の予想問題集にも掲載されていること、があげられます。
結果的に網羅型を完璧にしておけば他の予想問題集もカバーできる部分が多いです。
また、他の予想問題集は掲載されている問題が3回分程度と少ないのに対し、網羅型は8回分と多いのも利点です。
そのため、過去問題集や網羅型がほぼ完ぺきで他の問題に取り組んでみたいという方であれば他の予想問題集に手を出すのはありかと思います。
試験待機中や休憩時間中に行っていたこと

TikTokを見てリラックスしていました。
YouTubeで芸人のリップグリップの岩永さんという方が、大学受験日の休憩中にジェンガをして遊んでいたといっていました。
詳細は忘れましたが、試験日だからと言って特別なことをせず普段通りにするほうがいい、というようなことを言われていたかと思います。
それを真似し、普段休憩時間中にしているTikTokを見るようにしてみました。
これが試験結果に効果があったかどうかは不明ですが、間違いなくリラックスはできて試験を受けることはできました。
さいごに
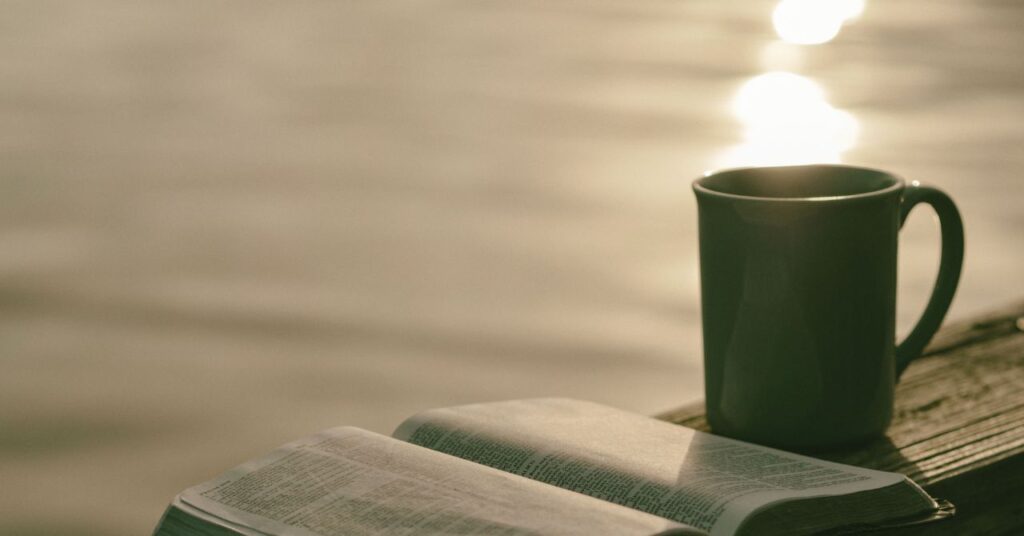
今回は、日商簿記1級についてでした。
今までいろんな資格勉強をしてきましたが、一番難しかったです。
ですが自己採点が86点だった時の達成感と開放感はほんとに気持ちがいいものでした。
日商簿記1級の受験を考えている方、不合格となった方に私の勉強方法が少しでも参考になればうれしいです。
ここまで読んでいただいてありがとうございました。




コメント